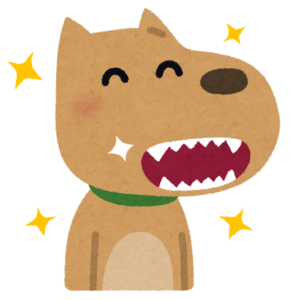春は要注意!ノミ・マダニがもたらす皮膚疾患と感染症について
こんにちは!東京都大田区大森のイース動物病院です。
春の暖かい陽気は、人にとってもペットにとってもお出かけ日和。しかし、その裏で密かに活動を始めているのが「ノミ」と「マダニ」です。これらの寄生虫は、犬や猫の皮膚に悪影響を与えるだけでなく、時に命にかかわる病気を媒介することもあります。
今回は、春に増加するノミ・マダニによる皮膚疾患や、媒介される病気について詳しく解説します。正しい知識と対策で、大切な家族であるペットを守りましょう。
ノミとは?マダニとは?
ノミとは
ノミは寄生性の昆虫で、動物の血を吸って生きています。最も一般的なのは「ネコノミ」で、犬にも猫にも寄生します。成虫は体長1~3mmほどで非常に小さく、ジャンプ力が非常に高く、動物の体に飛び乗って吸血を始めます。
マダニとは
マダニはダニの中でも大型で、肉眼でも確認できる節足動物です。草むらや森林などに生息しており、動物が通るときに体に取りつき、皮膚にかじりついて数日かけて吸血します。特に「フタトゲチマダニ」や「シュルツェマダニ」などが日本で多く見られます。
ノミ・マダニによって起こる皮膚疾患
ノミアレルギー性皮膚炎(FAD)
ノミの唾液に含まれるアレルゲンが原因で、強いかゆみと皮膚炎を起こします。以下のような症状が見られます:
- 激しいかゆみ
- 皮膚の赤みや湿疹
- 被毛の脱毛(特に背中から尾にかけて)
- かきむしりによる傷や出血
1匹のノミに刺されただけでも強い症状が出ることがあるため、重症化しやすく、早期の対策が重要です。
マダニによる皮膚炎・刺咬性皮膚炎
マダニが皮膚に吸着し、数日間吸血することでその部分に炎症や腫れが生じます。また、マダニの取り残しによって皮膚に異物反応が起こり、化膿することもあります。
- 吸着部位のしこり
- 赤みやかゆみ
- 二次感染(膿、臭い)
マダニは皮膚にしっかりと食いつくため、無理に引き抜くと口器が皮膚内に残ってしまうリスクがあり、獣医師による処置が必要です。
ノミ・マダニが媒介する重大な感染症
ノミが媒介する病気
- 瓜実条虫症(うりざねじょうちゅう) ノミを介して犬猫に感染する寄生虫で、ノミを舐めて体内に取り込むことで腸内に寄生します。 - 主な症状:肛門周囲のかゆみ、体重減少、下痢など。
- 猫ひっかき病(バルトネラ症) ノミに感染した猫が人を引っかくことで人にうつる人獣共通感染症です。 - 主な症状:リンパ節の腫れ、発熱、頭痛など。 - 特に免疫力の弱い人には重症化の恐れがあるため注意が必要です。
マダニが媒介する病気
- 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) ウイルスを持ったマダニに刺されることで感染します。人にも犬猫にも感染することがある非常に危険な病気です。 - 主な症状:発熱、嘔吐、下痢、出血傾向、死亡率が高い。 - 特に西日本を中心に発症例が増えています。
- バベシア症 バベシアという原虫が赤血球に寄生し、破壊することで貧血を起こします。 - 主な症状:元気消失、食欲不振、発熱、黄疸、尿の色の変化。 - 特に犬で多く見られます。
- ライム病 細菌性の人獣共通感染症で、マダニが媒介します。 - 主な症状:発熱、関節炎、歩行異常、筋肉痛など。
ノミ・マダニからペットを守るための予防対策
1. 定期的な予防薬の使用
- スポットタイプ(背中に垂らす)
- 経口タイプ(チュアブル)
- 首輪タイプ(有効成分が持続)
これらは月に一度の投与が一般的ですが、種類によって効果の持続期間が異なるため、獣医師と相談して選びましょう。
2. 室内外の環境整備
- カーペットやベッド、ソファの掃除・洗濯
- 庭やベランダの雑草・落ち葉の処理
- 動物との接触が多い場所をこまめに掃除
ノミやマダニの卵や幼虫は、環境中に潜んでいることも多いため、徹底した掃除が大切です。
3. お散歩時の注意点
- 草むらや山道を避ける
- お散歩後に全身チェック(特に耳の中、足の付け根、首周り)
- 長毛種は念入りに!
飼い主が注意すべきポイント
- ノミ・マダニは1年中活動する可能性がありますが、特に春〜秋にかけて要注意!
- 室内飼いの犬猫でも100%安全とは言い切れません。
- 一度寄生されると駆除が大変なので、予防が一番の対策です。
- 人への感染のリスクもあるため、家族全体での意識が重要です。
まとめ
ノミやマダニは、小さな体で大きな被害をもたらす寄生虫です。ペットの皮膚疾患だけでなく、命に関わる病気を媒介する危険もあるため、春先からの予防は必須です。
「うちの子は大丈夫」と油断せず、定期的な予防薬の使用や生活環境の管理を徹底することで、大切なペットの健康と家族の安全を守りましょう。